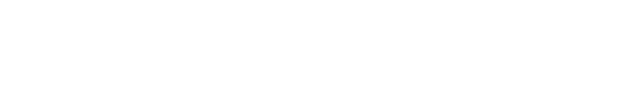PPPD (持続性知覚性姿勢誘発めまい)
めまいの診療、特に急に起こってくる急性めまいでは、中枢性めまいと末梢性めまいの鑑別が重要です。当院では頭部MRIや重心動揺検査などで検査で、ほとんどの方が末梢性めまいの診断となり、この場合は通常の鎮暈薬内服にて良くなることが多いです。めまいというと、ほとんどの場合こういった急性めまいをさすことが多いと思いますが、めまいが長期にわたって続き、生活に支障をきたす慢性めまいも少なからず経験します。
一般的に、めまいの症状が3か月以上続くと「慢性めまい」といい、その原因としては、多い順に①PPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい)、②心因性めまい、③前庭機能代償不全、④診断がつかないめまい症、などがあります。最も多いとされるPPPDは2017年に提唱された比較的新しい概念であり、以下のような特徴があります。
【症状】浮動感、不安定感、非回転性めまいのうち一つ以上が、3ヶ月以上にわたってほとんど毎日存在する。具体的には「ふわふわする」「頭が重い」「地に足がつかない」などの感覚。
【誘因】持続性の症状を引き起こす特別な誘因はないが、①立つ、歩く、頭や視線を動かすことで悪化、②人混みや視覚刺激が多い場所(スーパー、駅など)でも悪化、などの特徴がある。
【先行疾患】PPPDを発症させる頻度の高い病態は、末梢性または中枢性の前庭疾患(PPPD 症例の25~30%)、前庭性片頭痛の発作(15~20%)、パニック発作または不安障害(それぞ れ15%)、脳 し ん と う ま た は む ち 打 ち 症(10~15%)、自律神経障害(7%)など。
頭部MRIや耳鼻科的な検査では異常が認められないことが多く、不安や抑うつと共存しやすい病態のようです。治療は、PPPDの病態を理解したうえで、①前庭リハビリテーション、②薬物療法(SSRIなどの抗うつ薬)、③認知行動療法、などが行われます。